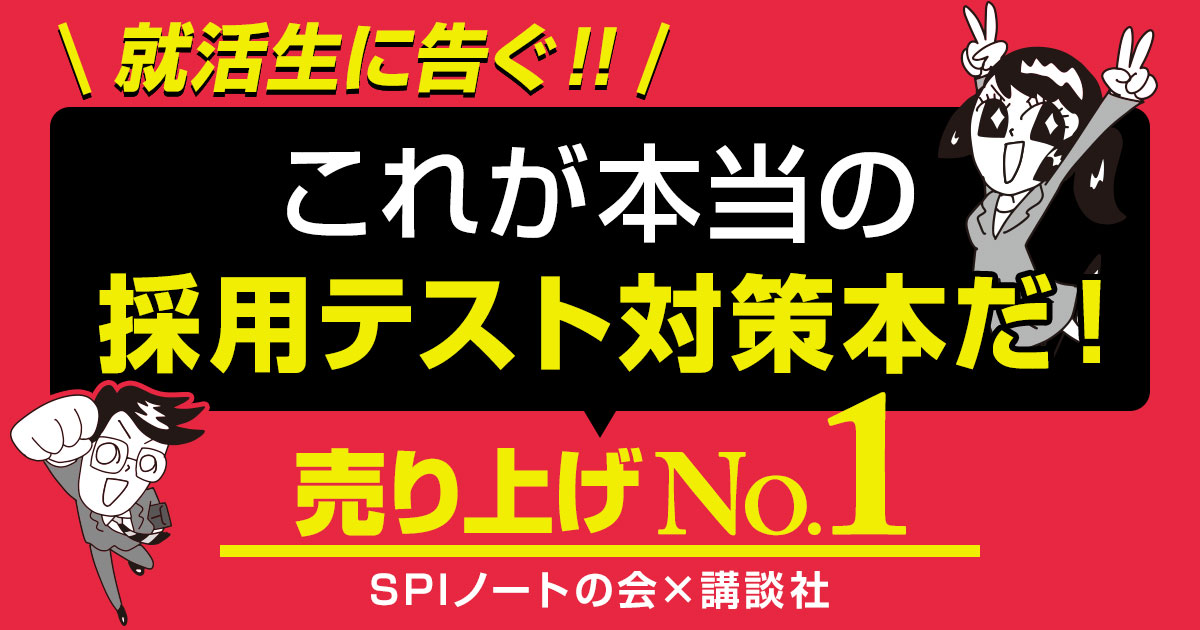就活生のみなさん、筆記試験対策していますか?「SPI?玉手箱?なにそれ美味しいの?」と筆記試験に頭を抱えていませんか?
大学受験が終わってホッとしたのも束の間、「就活では筆記試験があります」と聞いて対策について考えると胃がキリキリ…なんてこと、ありますよね。実際、就職活動の選考ではほとんどの企業が筆記試験やWebテストを導入しているのです。避けて通れぬ関門とはいえ、「また筆記試験かよ!」とプレッシャーを感じるのは当然。でも大丈夫、あなただけじゃありません。毎年SPIだけでも200万人以上が受験していると言われており、対策方法も確立されています。
この記事では、そんな就活の筆記試験について、なぜ必要なのかから主要テストの違い、効果的な対策法を解説していきます!
就活で筆記試験を行う目的は?
ところで、なぜ企業は就活でわざわざ筆記試験なんて行うのでしょう?エントリーシートや面接だけじゃダメなの?と疑問に思いますよね。
理由はちゃんとあります。
筆記試験には、面接では評価しきれない基礎能力を把握したり、一度に大量の応募者から絞り込んだりする役割があります。面接だけでは測れない「地頭の良さ」や「基礎学力」、「論理的思考力」などを客観的に見るために、多くの企業が就活で筆記試験を活用しているのです。要は、筆記試験=企業版フィルタリング装置。就活では応募者全員といきなり面接するのは現実的に難しいので、まず筆記試験で一定水準をクリアした人だけを次に進ませよう、というわけです。
また、筆記試験には志望者にとっても“チャンス”という側面があります。面接では緊張してうまく話せない人でも、筆記試験で高得点を取ればアピール材料になりますし、何より学力や対策の努力で挽回できる余地があるのです。企業も「この子、面接は大人しめだけどテストできるじゃん!」と評価してくれるかもしれません。筆記試験は決して意地悪で課されているのではなく、あなたの持ち味を別角度から見せる場でもあるんですね。
以下に、企業が就活で筆記試験を行う目的を6つ書きました。
1. 応募者の基礎能力を測る
就活の筆記試験は、応募者の基礎学力や論理的思考力を客観的に評価するために使用されます。特に、SPIや玉手箱などの試験では、語彙力や計算力、推論能力が問われるため、企業はこれらを通じて応募者の基本的な能力を見極めます。就活は新卒採用の場合、実務経験がないため、学力や思考能力が重要な指標となります。
2. 応募者のスピードと正確性を確認する
就活の多くの筆記試験には時間制限が設けられており、スピードと正確性が問われます。これにより、応募者が業務の中でどれだけ効率的に作業をこなせるかを推測することができます。例えば、急いで決定を下す必要がある場面や大量のデータを迅速に処理しなければならない業務では、この能力が重要です。
3. 面接前のフィルタリング
就活で面接に進む前に、大量の応募者を絞り込むために筆記試験を利用します。企業は、就活では応募者全員に面接を行うことが現実的に不可能であるため、筆記試験で一定の基準を設け、事前に選考を行います。このようにして、面接に進む候補者を絞り込むことで、限られた時間を有効に使うことができます。
4. 応募者の適性や性格を知る
就活で使わらえる一部の筆記試験では、性格や適性も測定されます。例えば、SPIの「性格検査」や玉手箱などでは、応募者の協調性やストレス耐性、仕事に対する姿勢を推測するための質問が含まれています。これにより、企業側は応募者がチームで働けるか、業務のプレッシャーに耐えられるかなどを判断します。
5. 業務に必要な知識・技能の有無を確認する
特定の業界や職種に応募する際、企業は専門的な知識や技能が求められることがあります。例えば、IT企業ではプログラミング能力や論理的思考、金融業界では数値的な能力や計算力が重要視されます。これらの能力を就活の筆記試験で確認することで、応募者が実際に業務に適しているかを見極めることができます。
6. 公平で客観的な選考を実現する
就活の筆記試験は、面接のように主観が入ることなく、公平かつ客観的に評価することができます。面接では、面接官との相性やコミュニケーション能力が重視されがちですが、筆記試験では全ての応募者が同じ基準で評価されるため、選考の透明性を高める効果があります。
![]()
【就活の筆記試験】SPI・玉手箱・CAB・GABって何が違うの?
さて、就活での「筆記試験」と一口に言っても実はいろいろ種類があります。就活生を悩ませる主な試験たちをざっくり紹介しましょう。「聞いたことあるけど違いはよく知らない…」というあなた、ここで一緒に整理して対策していきましょう。
【就活の筆記試験】SPI(エスピーアイ)
最もポピュラーな就活の筆記試験、適性検査として知られるSPIは【Synthetic Personality Inventory】の略称で、「能力検査(言語・非言語)」+「性格検査」で構成されています。
とにかく実施企業数No.1で、多くの就活生が避けて通れません。内容は中学~高校レベルの国語(語彙・長文読解など)と数学(算数・推論問題など)が中心。問題数はそれなりですが各問題ごとに時間制限があるケースが多く、時間配分との戦いです。「学生時代にこんなのやったな~」という問題が幅広く出るので、基本を対策すれば得点アップが狙えます。受検方式はいくつかあり、テストセンター会場でPC受検、自宅PCでWeb受検、紙でマーク式…と企業により様々ですが、どの形式でも出題範囲は概ね似ています。まずはこのSPI対策から始める就活生が多いですね。
【例題①】
言語(語彙)
問題:
「うってつけ」の意味に最も近いものを選びなさい。
①絶好の
②面倒な
③無理な
④使いにくい
答え: ①. 絶好の
【例題②】
非言語(数的推理)
問題:
ある工場で、5人の作業員が6時間で100個の製品を作ります。この作業員が10人になったとき、同じ条件で製品を作るには何時間かかるか。
①3時間
②4時間
③5時間
④6時間
答え: ①. 3時間
(解説:作業員数が2倍になれば時間は半分になります)
【就活の筆記試験】玉手箱(たまてばこ)
名前だけ聞くとおめでたい感じ(?)ですが、こちらもSPIに次いで導入企業が多い筆記試験です。日本SHL社が提供しており、科目は言語・計数(非言語)・英語・性格検査など。
特徴はとにかく問題数が多い&スピード重視なこと。各科目ごとに制限時間が設定され、一度に大量の問題を解く必要があります。「長文読解20問を10分で」といったスリリングな設定もあり、とにかく速く正確に解く対策が求められます。SPIと違い一問ごとの時間制限はなく科目単位の制限時間なので、自分で時間配分を考える力が対策の鍵になります。内容自体は基本的な読解力・計算力を問うものですが、問題文1つにつき設問が複数ある形式が多く、一度ペースを乱すと焦りがち。玉手箱という名前に油断していると「開けてビックリ!時間切れで真っ白…」なんてことにも。SPI対策プラス、玉手箱独特の形式にも慣れておくと安心です。
【例題①】
言語
問題:
次の文章を読んで、最も適切なものを選びなさい。
「昨今、デジタル技術の発展により、企業の在り方が大きく変わりつつある。」
①デジタル技術の発展が企業に与える影響は小さい
②デジタル技術が進化していることにより、企業は変わりつつある
③デジタル技術は企業にとってあまり重要ではない
④企業はデジタル技術に逆行している
答え: 2. デジタル技術が進化していることにより、企業は変わりつつある
【例題②】
計数(非言語)
問題:
次の計算式の結果を選んでください。
45 × 7 ÷ 9
①35
②39
③40
④44
答え: ② 39
(解説:45 × 7 = 315、315 ÷ 9 = 35)
【就活の筆記試験】CAB(キャブ)
エンジニア・プログラマー志望向けの就活に使われることが多い適性検査です。【Computer Aptitude Battery】の略で、その名のとおりコンピュータ職適性を見る筆記試験です。
内容がユニークで、暗算・法則性・命令表・暗号といったパズル的問題+性格検査という構成。例えば「暗号」は記号変換問題、「命令表」は簡易的なプログラムのような表読み取り問題など、一瞬ギョッとする出題が並びます。難易度もSPIより高めと言われ、本気で対策しないと太刀打ちできません。就活でIT系を目指す人には避けられない試験で、紙で行う従来型CABとWebで行うWeb-CABがあります(Web版の方が問題数が多く時間がさらにシビア)。プログラミング言語は出てきませんが、論理的思考力や集中力をかなり要求される試験です。
【例題】
論理的思考(法則性)
問題
次の図形に続くパターンを選びなさい。
■ → ◆ → ■ → ◆ → (?)
①■
②◆
③○
④△
答え: 1. ■
(解説:パターンは「■ → ◆」が交互に繰り返されるため)
【就活の筆記試験】GAB(ギャブ)
こちらは就活で総合職向けの高度な適性検査として導入されることが多いテスト。【Graduate Aptitude Battery】の略です。
商社や金融、コンサルなど知的レベルを重視する業界で採用されることが多く、いわばSPIのハイレベル版です。出題範囲は言語理解(長文読解の正誤判断など)・計数理解(グラフや表の読み取り計算)・性格検査が中心で、形式自体はSPIに似ています。ただし問題の難易度や制限時間が厳しく、よりスピーディーかつ高正確に解く力が求められるのが特徴です。場合によっては英語試験が加わることもあります(※とくに外資系や一部企業ではGABの派生で英語付きの「C-GAB」を実施)。要するに難易度高めのSPIと思ってもらえればOKですが、問題傾向が少し違うため専用の対策は必要です。難しい分、実施企業は限られますが、志望業界によっては避けられないのでしっかり対策しましょう。
【例題】
言語理解(長文読解)
問題:
「最近では、オンラインショッピングが急速に普及し、多くの消費者が自宅から商品を購入するようになった。この流れに乗り、企業は消費者のニーズに合わせた迅速な配送サービスを提供し始めている。」
次の選択肢の中で、この文章に最も関連するものはどれか。
①オンラインショッピングの普及によって、配送サービスが改善された
②消費者は従来の方法で商品を購入している
③企業は消費者のニーズに応える必要はない
④オンラインショッピングは普及していない
答え: ①. オンラインショッピングの普及によって、配送サービスが改善された
他にも細かい適性検査はいくつか存在しますが、就活の筆記試験として主要どころは大体この4種類です。あなたが受ける企業はどのテストを課してくるのか、エントリー前に調べておくと効率的ですよ。「うわ、あの企業は玉手箱だった!」となれば、その対策に重点を置けますし、「IT企業だからCAB出るかも…」と分かればしっかり対策もできます。まずは就活で代表的な筆記試験の特徴を把握しておくことが、戦略立ての第一歩です。
![]()
就活の筆記試験攻略!効果的な対策法あれこれ
就活の筆記試験も試験である以上、しっかり対策すれば点数は上がります。なんの準備もせず本番に挑むのは流石にリスキー。ここでは、多くの先輩就活生が実践した効果的な対策法をいくつか紹介します。「勉強とか久々でやる気出ない…」という人も、できるものから対策してみましょう!
【筆記試験対策】参考書・問題集で基礎固め
就活の筆記試験対策には王道ですがやはり市販の参考書や問題集は強い味方。SPI用、玉手箱用、CAB/GAB用など、それぞれ専門の対策本が出ています。一冊やり込めば出題パターンに慣れるので安心感が違いますよ。
例えば「これが本当のSPI3だ!」などが定番です。初めは解けなくても解説を読んで理解し、何度も繰り返すことで徐々にコツがつかめます。出題範囲の網羅という点で参考書は優秀なので、就活を始めるときにまず1冊選んで潰してみましょう。
就職試験対策の第一人者「SPIノートの会」の採用テスト対策本シリーズ!──SPI3をはじめ、就活生のみなさんが知りたい情…
【筆記試験対策】スマホアプリでスキマ学習
就活の筆記試験対策には通学時間やちょっとした空き時間もバカにできません。SPI対策アプリなどをスマホに入れておけば、いつでもどこでもお手軽に問題演習で対策ができます。
例えば「SPI言語Lite」や「SPI非言語Lite」(Study Pro)といった無料アプリは、苦手問題を優先出題する機能もあり効率的な対策方法です。最近は一般常識や時事問題の一問一答アプリも人気で、ニュースに疎い人の強化に役立ちます。スマホならゲーム感覚で続けやすいので、スキマ時間をフル活用して実力アップにつなげましょう。
App Store でStudy Proの「SPI Lite 【Study Pro】」をダウンロード。スクリーンショット…
It will be the SPI language [Study Pro] trial version of (th…
【筆記試験対策】模擬試験で腕試し
就活の筆記試験は可能なら模試(模擬試験)にチャレンジして対策してみるのもおすすめ。
大学のキャリアセンターや就活支援サービス、一部の参考書付録などで模擬テストを受けられる場合があります。本番形式で時間を計って解いてみることで、自分の現状スコアや弱点分野が見えてきます。「時間が全然足りなかった!」とか「意外とケアレスミスしてた」など課題を発見したら、そこを重点的に対策しましょう。模試は緊張感に慣れる良い機会にもなるので、ぜひ本番前に一度はシミュレーションしてみてください。
【筆記試験対策】勉強計画を立てコツコツ継続
筆記試験対策は短期詰め込みより計画的なコツコツ勉強が効果的と言われます。「最低30時間、できれば60時間程度の対策は必要」とも言われています。いきなり60時間と聞くと尻込みしますが、例えば試験の1~2ヶ月前から毎日1時間ずつ進めれば十分届く数字です。
一気に詰め込むと身につかない上にストレスも溜まるので、授業やバイトの合間に少しずつ学習習慣をつけましょう。スケジュール管理も大事ですよ!エントリー締切やテストセンター予約日に逆算して、「○月○日までに非言語を一通り終える」などマイルストーンを決めておくと計画が立てやすいです。自分なりのペースで構わないので、継続して取り組むことで着実に力がついていきます。
「落ちたらどうしよう…」その不安に寄り添う
どれだけ対策しても、不安は完全には消えないですよね。「もし筆記で落とされたら、自分は社会に必要とされない人間なんじゃ…」なんてネガティブ思考に陥る夜もあるでしょう。でも声を大にして言います――筆記試験の結果が人生のすべてを決めるわけじゃない! たとえ出来が悪くても、採用されるケースもありますし、逆に筆記満点でも面接でご縁がなければ内定は出ません。
実際、筆記試験で失敗しても挽回のチャンスはあります。企業によっては筆記の合否を絶対視せず、他の選考要素と総合判断してくれるところもあります。
「今回ダメでも次があるさ!」くらいの開き直りも時には必要です。一社や二社、筆記で落ちたからといってあなたの価値が否定されたわけではありません。就活はトータル勝負。筆記が苦手でも、エントリーシートや面接でアピールできる強みを磨いておけばカバー可能です。
とはいえ、「連続で筆記落ち続けたらどうしよう…」と不安な人もいるでしょう。その場合は、戦略を見直すサインかもしれません。対策不足であれば勉強時間を増やす、志望業界を広げて筆記試験無しの企業も検討してみる、大学の就職支援課に相談してみる…など打てる手はあります。自分ひとりで抱え込まず、友人や先輩と情報交換するのも効果的です。「あの会社のテスト難しかったよね~」「この問題集おすすめだよ」なんて話せば少しは気が晴れるものです。とにかく大事なのは、筆記試験の失敗で自分を責めすぎないこと。落ち込んでも立ち直って次に向かうタフさも、就活では大事な力ですよ。
「サマーインターン、全部落ちた…」「もう就活うまくいかないかも...」そんなふうに落ち込んでいませんか?安心してください。サマーインターンに全落ちしたからといって、就活が終わるわけではありません。むしろここからの行動次第で、いくらで[…]
![]()
筆記試験は通過点!自信を持って次へ進もう
最後に強調したいのは、筆記試験はゴールではなく通過点だということ。就活の本丸はこの先の面接やグループディスカッションなどで、筆記はあくまでその入り口にすぎません。極端な話、筆記試験は「足切りラインさえ越えればOK」というケースがほとんどです。満点を取って表彰されるわけでもなし、合格基準をクリアすればそれ以上は評価に大差ないことも多いんです。だからこそ、深刻に思いつめすぎず「ちゃっちゃと通過してやるか!」くらいの気持ちで挑んでみましょう。
筆記試験に合格したら、次はいよいよあなた自身の人となりを伝えるステージが待っています。企業も最終的には人柄や熱意、フィット感を見て採用を決めます。筆記ができるに越したことはないですが、それだけで合否が決まるわけではありません。適度に肩の力を抜いて、「このテストを突破したら志望企業で働くチャンスが見えてくる!」という前向きなイメージを持ってください。
筆記試験が終わったら読みたい記事
就職活動では、面接だけでなくグループディスカッションが課されることがあります。グループディスカッションは、限られた時間の中で複数人が話し合い、結論を導き出す選考形式です。初めて参加する人にとっては、「どのように発言すればいいのか」「うまく話[…]
最近、転職活動をしている中で、「カジュアル面談」の案内をされたことがある人も多いでしょう。この記事では、「カジュアル面談とは?」「カジュアル面談と面接はどう違うの?」「カジュアル面談に参加するとき、事前に準備することはある?」「お礼[…]
今日は大事な面接日。しかし、まさか面接当日に体調不良になってしまった!!大事な面接当日に体調不良で動けなかったら、せっかくの面接にも行くことができません。そんな時に大事なのは、マナーを守って適切な行動がとれるかどうかです。[…]